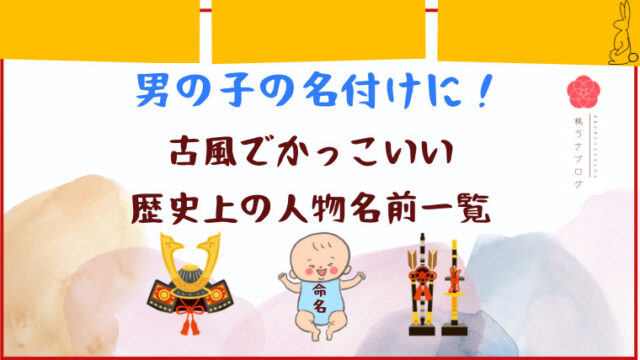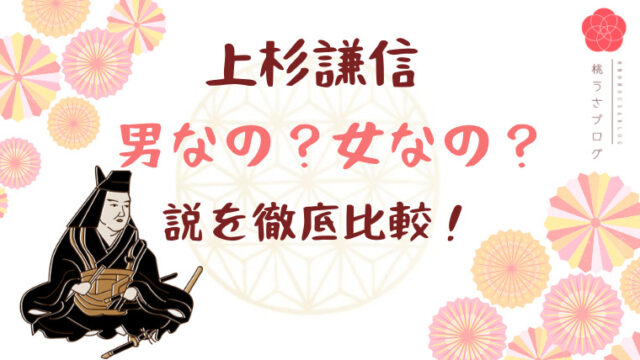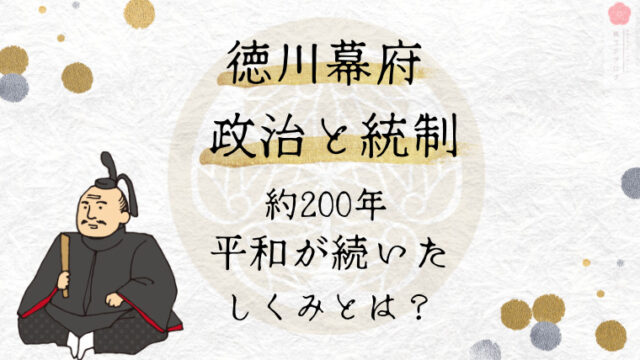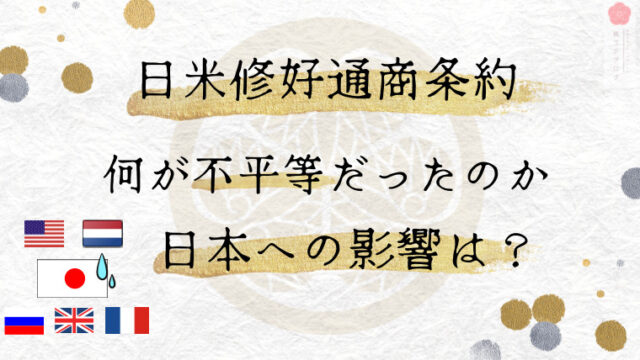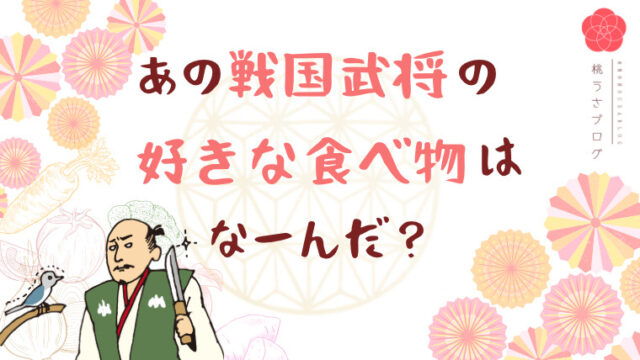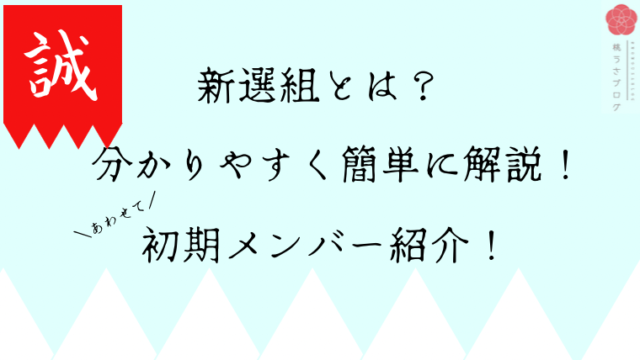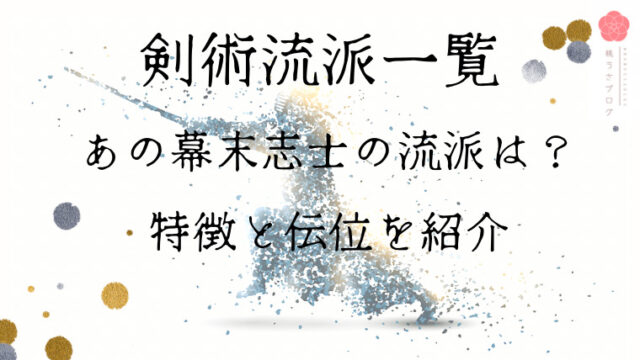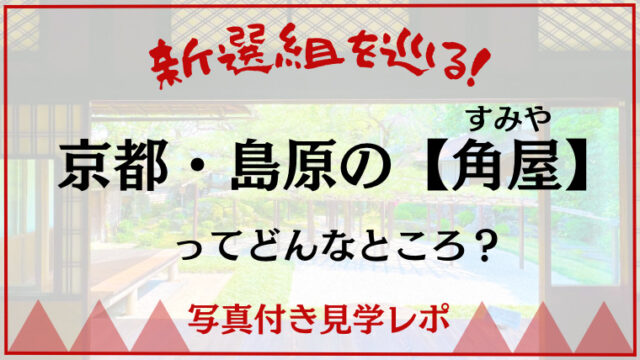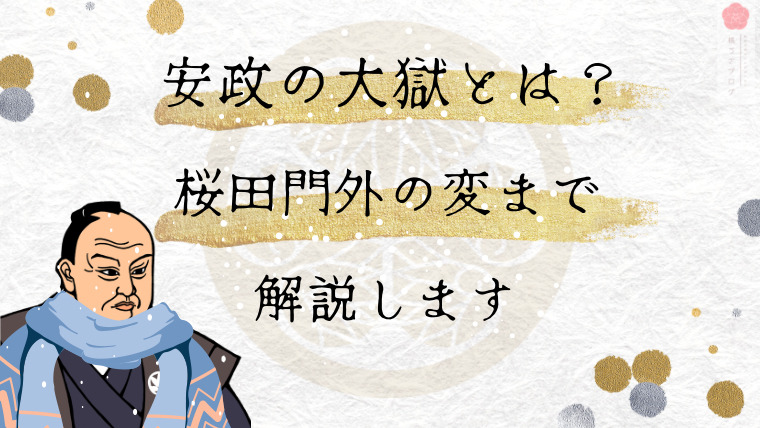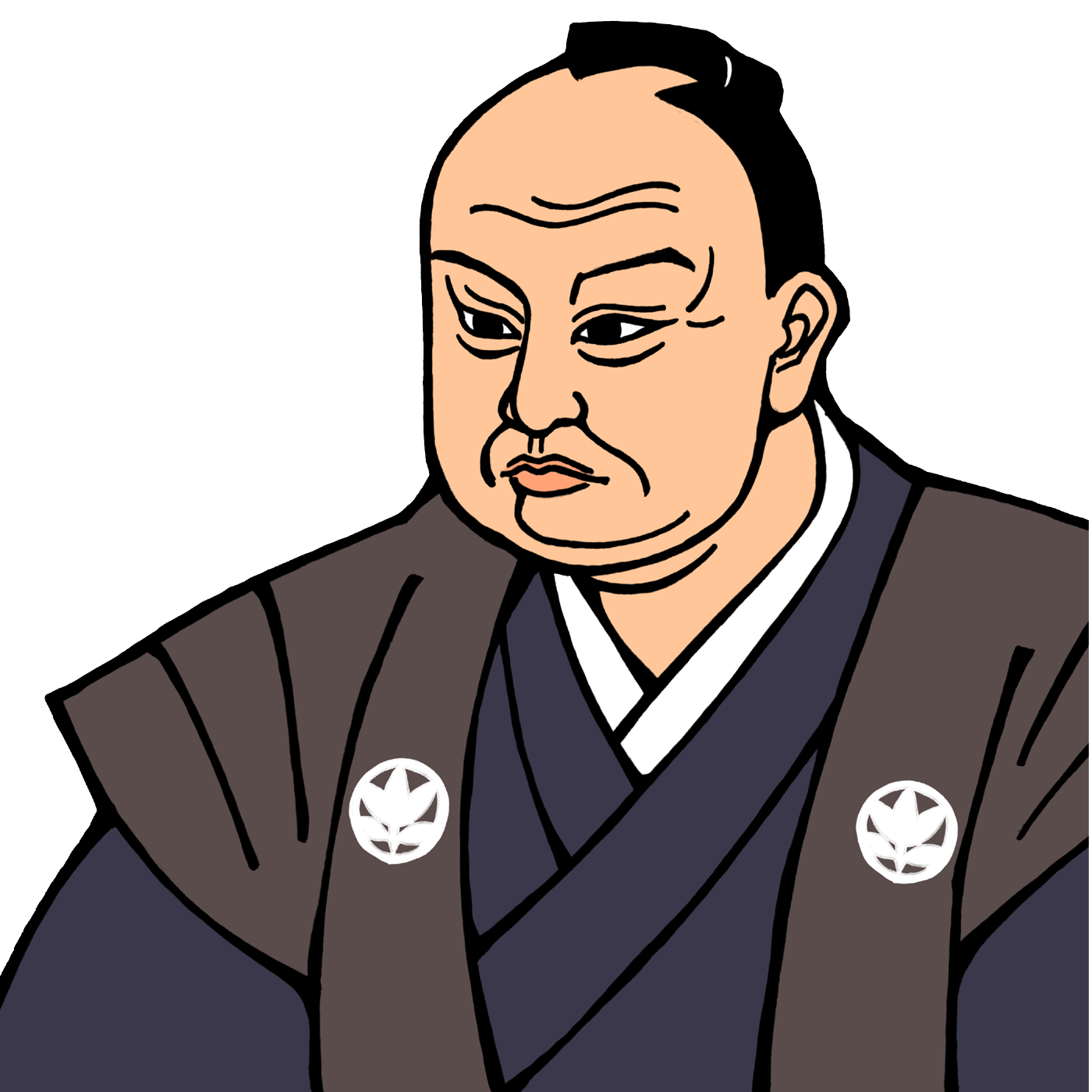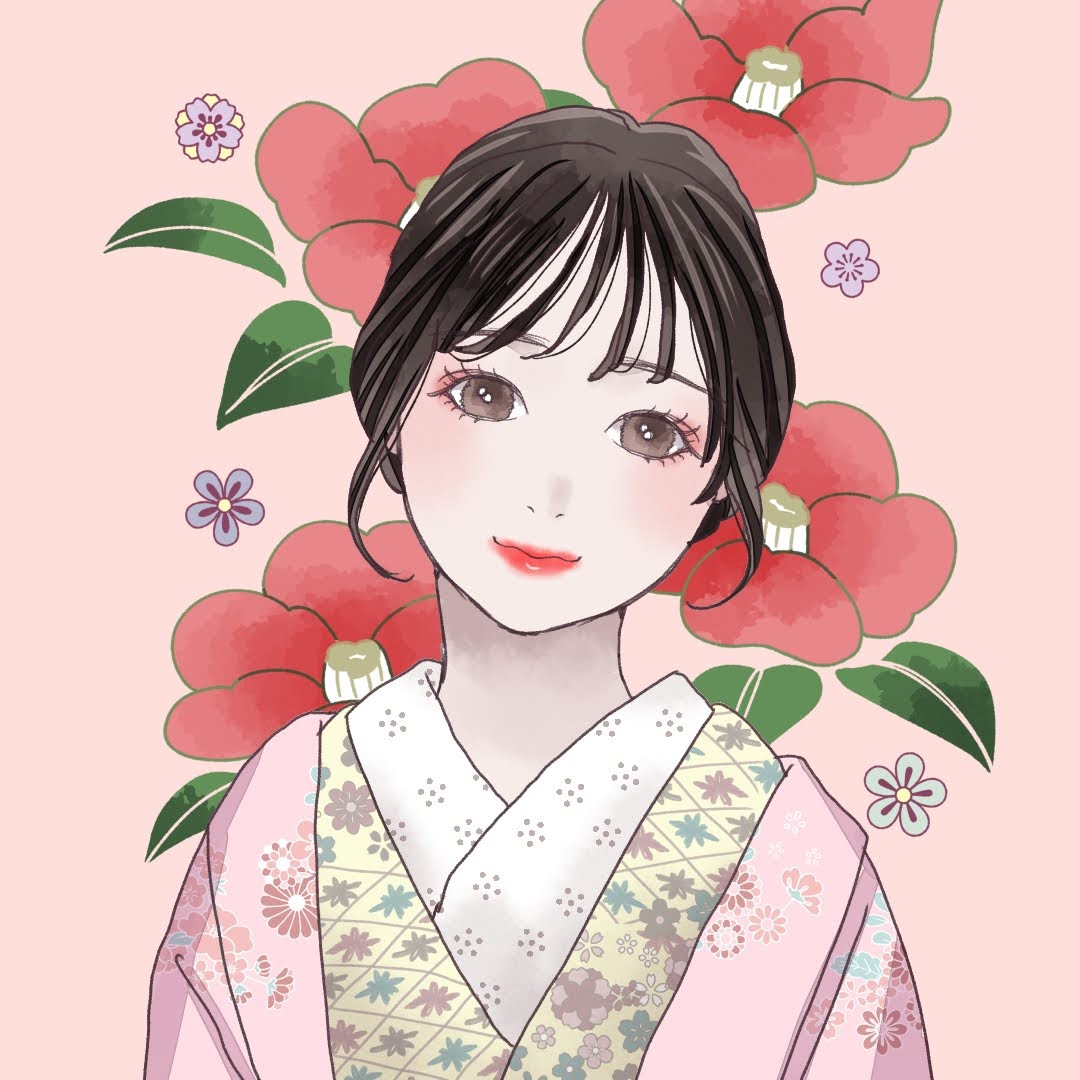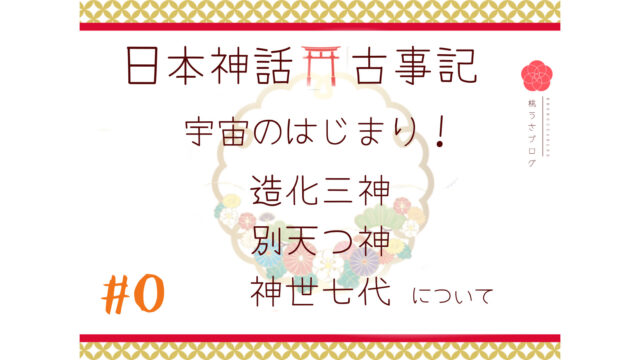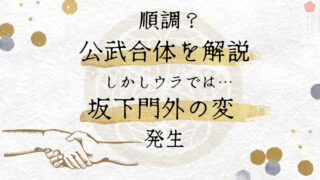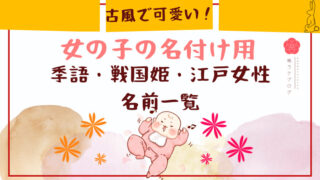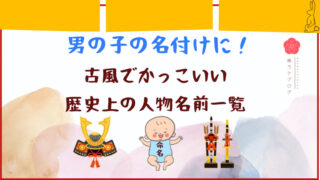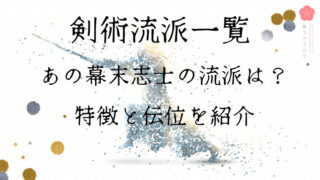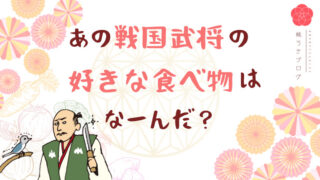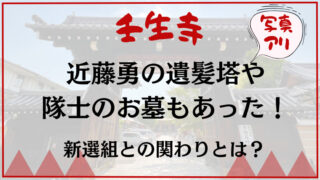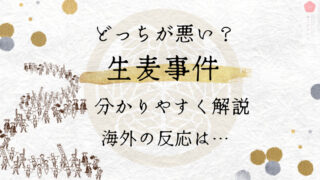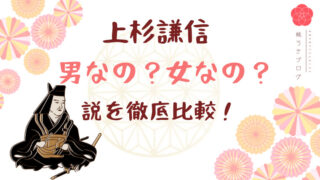安政の大獄 から 桜田門外の変 までの流れを、分かりやすく解説します。
今回の記事はこのような方におすすめ!
-
安政の大獄って何?
-
安政の大獄は「なぜ・いつ」起きたの?
-
桜田門外の変と関係あるの?
おそらく学校では「なぜ」の部分は、教わらないと思います。(少なくとも私の学生の頃の記憶にない…。)
そのため「井伊直弼 は怖い人」というイメージがあるかもしれません。
家康時代の徳川四天王だった井伊直政の「赤備え」に絡めて、当時の人々も直弼のことを「井伊の赤鬼」と呼んで恐れたそうです。
ですが幕府のウラ事情が分かれば、直弼の行動の理由が見えてきますよ。
※今までの幕末記事を読んでくださっている方は、目次「戊午の密勅」までジャンプしていただくといいかなと思います。
お手数おかけします。
\ランキング参加中/
![]()
![]()
↑良かったらポチッと応援お願いします♪励みになります!
安政の大獄とは
 安政の大獄とは、安政5年〜安政6年の間に行った、政治弾圧事件。
安政の大獄とは、安政5年〜安政6年の間に行った、政治弾圧事件。
この弾圧を主導したのが、幕府の大老・井伊直弼でした。
弾圧の対象となったのは、「一橋派」や「尊王攘夷派」の人々です。
「一橋派」については、後ほど説明しますね。
結果的にはこの弾圧により、8名が処刑されて、100名以上が謹慎などの処罰を受けました。
それでは一体なぜ、井伊直弼はこのような弾圧に踏み切ったのでしょうか?
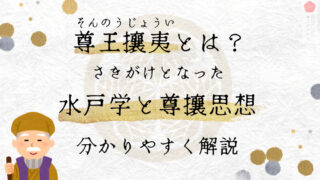
外国の脅威と幕府の改革
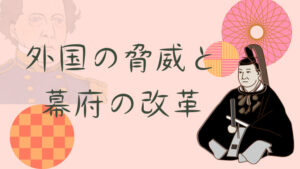 時を戻そう。
時を戻そう。
嘉永6年にペリーが日本にやってきました。
外国の脅威に現実味が増してくることになります。
もともと政治ができるのは「譜代大名」だけでした。
そこで時の老中首座・阿部正弘が改革を行います。
阿部正弘の改革が、親藩や外様大名が「政治に口出しできる」きっかけになりました。
これが幕府内の混乱に繋がっていきます。
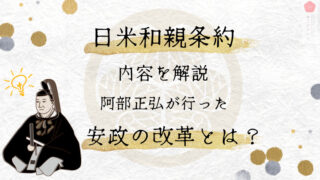
将軍継嗣問題
 将軍継嗣問題とは「次の14代将軍を誰にするのか」という問題です。
将軍継嗣問題とは「次の14代将軍を誰にするのか」という問題です。
ここで幕府の意見が分裂してしまいます。
譜代大名・井伊直弼を筆頭に、同じ譜代や保守派の親藩などは、「徳川慶福」を次の将軍に推す、南紀派と呼ばれました。
南紀派は従来からの血筋を重視した、徳川の伝統的な受け継ぎ方です。
「待った」をかけたのは、親藩の水戸藩・徳川斉昭(慶喜の実父)や、外様の薩摩藩・島津斉彬などの一橋派。
一橋派は国家の危機を乗り越えられる有能な人物、慶福よりも年上の「一橋慶喜」を推していました。
将軍は我々が決める!
従来の伝統を重んじる直弼がそう思っているところ、安政5年4月23日に直弼は大老に任命されました。
大老は幕府の臨時職でありながら、将軍の次くらいの権力があります。
井伊直弼が大老になったことで、次の将軍は「徳川慶福」に決めてしまします。
仮に「一橋慶喜」が将軍になってしまうと、父である水戸藩主・徳川斉昭ら尊王攘夷派の力が増すことになります。
そうなると政権を奪われかねません。
「戦争を回避するため、開国は仕方ない」と考える幕府にとって避けたいところでした。
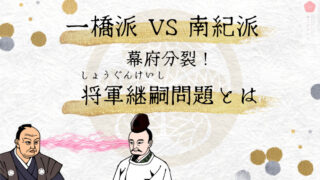
日米修好通商条約
 安政3年7月には、日米修好通商条約を結ぶため、ハリスが来日します。
安政3年7月には、日米修好通商条約を結ぶため、ハリスが来日します。
幕府内では水戸藩・徳川斉昭らをはじめとする尊王攘夷派が条約調印に反対。
尊攘派を黙らせるために、幕府は孝明天皇に条約調印の許可をもらいに行きます。
しかし天皇からの許可はもらえませんでした。
そんななか安政5年4月に、井伊直弼が大老になったことで、条約調印を迫られていた日米修好通商条約も進展。
安政5年6月19日には、日米修好通商条約が締結しました。
条約締結に徳川斉昭らは憤慨。
天皇の許可をもらわずに勝手に条約に調印するとは!
不届き者なり!
井伊直弼に抗議するため、徳川斉昭・慶喜・慶勝、松平慶永たちは江戸城に不時登城してしまいます。
不時登城…登城日以外の登城のことで、いわゆる押しかけ登城です。
江戸城は決められた日以外の登城は禁止されていました。
抗議の活動が裏目に出ます。
井伊直弼は徳川斉昭たちを、不時登城の罪で隠居・謹慎処分にしました。
慶喜は当分のあいだ登城禁止の程度。
これが安政の大獄の始まりです。
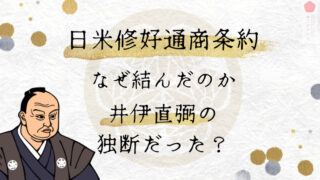
戊午の密勅
 戊午の 密勅 は、安政5年8月8日の出来事です。
戊午の 密勅 は、安政5年8月8日の出来事です。
幕府にはこの2日後に届きました。
戊午…安政5年の干支。
密勅…朝廷内の正式な手続きをしていない勅書。
-
日米修好通商条約を勝手に調印したことを説明せよ。
-
諸藩は幕府に協力して、※公武合体を目指すこと。
-
幕府は攘夷を推進すること。
-
この内容は水戸藩が諸藩にまわすこと。
※公武合体…朝廷と幕府が協力して、再び幕藩体制の強化をしようという考え。
お分かりいただけただろうか…。
そうです、問題は朝廷が幕府じゃなく水戸藩に直接手紙を送ったこと!
本来であれば、幕府に送らなければいけません。
これを幕府の家臣にあたる水戸藩に、朝廷が直接命令を下したことになります。
これは200年余りの幕府の政治体制を大きく揺るがし、秩序が崩れてしまうような大問題!
現在の幕府からしてみると、水戸藩に政権を乗っ取られてしまう危機です。
井伊直弼は幕府崩壊の危機から、戊午の密勅に関わった人物を、徹底的に弾圧することを決意しました。
この弾圧が安政の大獄。
処罰された人物
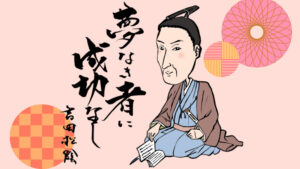 安政の大獄では多くの志士や公家が処罰されました。
安政の大獄では多くの志士や公家が処罰されました。
死罪8名、獄死6名、隠居・謹慎・流罪などの処罰者は100名以上に及びます。
| 安政の大獄で死刑になった人物 | |
| 長州藩 | 吉田 松陰(よしだ しょういん) |
| 福井藩 | 橋本 左内(はしもと さない) |
| 水戸藩 | 安島 帯刀(あじま たてわき) |
| 水戸藩 | 茅根 伊予之助(ちのね いよのすけ) |
| 水戸藩 | 鵜飼 吉左衛門(うがい きちざえもん) |
| 水戸藩 | 鵜飼 幸吉(うがい こうきち) |
| 儒学者 | 頼 三樹三郎(らい みきさぶろう) |
| (元)土浦藩 | 飯泉 喜内(いいいずみ きない) |
桜田門外の変
 桜田門外の変とは安政7年3月3日に、江戸城の桜田門の近くで、井伊直弼が暗殺された事件のことです。
桜田門外の変とは安政7年3月3日に、江戸城の桜田門の近くで、井伊直弼が暗殺された事件のことです。
暗殺した犯人は、水戸の※脱藩浪士17名と、薩摩の脱藩浪士1名。
 【桜田門】出典:国立国会図書館デジタルコレクション
【桜田門】出典:国立国会図書館デジタルコレクション
安政6年12月から、幕府は水戸藩に対して、天皇の勅書(戊午の密勅)の返却を求めました。
水戸藩は頑として返却を拒否するも、幕府も譲らず返却を催促。
弾圧に不満を持っていた水戸藩士は、ついにこれが引き金となって、雪が降るなか井伊直弼を暗殺。
※脱藩浪士…藩を脱けた志士のこと。
ただ白昼堂々の犯行だったので、暗殺というより、襲撃事件って感じですよね。
この暗殺事件により、幕府の権威は落ちてしまいました。
まとめ
今回のまとめ!
安政の大獄
安政5年〜安政6年の間に行った、政治弾圧事件。
この弾圧を主導したのが、幕府の大老・井伊直弼。
弾圧の対象となったのは、「一橋派」や「尊王攘夷派」の人々。
原因
- 将軍継嗣問題や日米修好通商条約を巡っての対立。
- 戊午の密勅。
安政の大獄の結果
多くの志士や公家が処罰された。
死罪8名、獄死6名、隠居・謹慎・流罪などの処罰者は100名以上。
桜田門外の変
安政7年3月3日に、江戸城の桜田御門の近くで、井伊直弼が暗殺された事件。
暗殺した犯人は、水戸の脱藩浪士17名と、薩摩の脱藩浪士1名。
原因
- 弾圧による不満。
- 天皇の勅書の返却を要求されたこと。
結果
幕府の権威が失墜。
安政の大獄は、ペリーが来航してからというもの、全部繋がって起きた出来事だったんですね。
ここから段々と時代は倒幕へと傾いていきます。
幕府も水戸藩も、日本を思う心は一緒なのに、切ないなぁと思ってしまいますね。
基本的に幕府も開国はしたくないけど、外国との戦争を避けるための決断だったため、こうしたジレンマを抱えています。
井伊直弼も幕府立て直しのため、ものすごい覚悟で行動していたのではないでしょうか。
あなたはどう思いましたか?